
「ファクタリングを使ったときの仕訳、どう処理すればいいの?」
「売掛金を早めに現金化したけど、勘定科目は何になるの?」
──そんなお悩みをお持ちの経理担当者や個人事業主の方も多いと思います。
ファクタリングは、売掛金を買い取ってもらうことで
資金を早く受け取れる便利な仕組みですが、
仕訳の考え方は「融資」とはまったく違います。
この記事では、**経理歴25年のFP(ファイナンシャルプランナー)**である筆者が、
ファクタリングの仕訳方法や売掛金処理のポイントを
具体的な例をまじえて、やさしく解説します。
🎯 本記事でわかること
- ファクタリング取引の会計上の位置づけ(融資との違い)
- 2社間・3社間それぞれの仕訳パターン
- 手数料の勘定科目と消費税の扱い
- 経理処理時に注意すべき実務ポイント
-1.png)
監修・執筆者:加藤ユウ(資金繰りナビ運営者)
・25年以上にわたり企業の資金繰り支援に従事
・融資交渉・キャッシュフロー改善を現場で推進
・ファイナンシャルプランナー(AFP)
資金繰り管理、融資交渉、業務効率化プロジェクトなどを歴任。
ファイナンシャルプランナー資格を保有し、法人・個人双方の資金戦略に精通。
現場で培った実務知識をもとに、正確で中立的な「資金繰り・ファクタリング」の情報をわかりやすく発信しています。
ファクタリングとは?売掛金を早めに現金化するしくみ
ファクタリングとは、売掛金(まだ入金されていない請求書)をファクタリング会社に買い取ってもらうサービスです。
これによって、本来は1か月後や2か月後に入金されるはずの資金を、最短即日で受け取ることができます。
たとえば――
9月末入金予定の100万円の売掛金を、95万円でファクタリング会社に譲渡した場合、
手数料(5万円)を差し引いてすぐに95万円の入金が受けられる、という仕組みです。
💡 ファクタリングのしくみをカンタンに言うと…
- 融資(借金)ではなく、「売掛金の売却」
- 利息ではなく、「手数料」を支払う
- 売掛先(取引先)に知られないタイプ(2社間)と、知られるタイプ(3社間)がある
この「売掛金の売却」という考え方が、仕訳処理の最大のポイントです。
次の章では、実際にどう仕訳すればいいのかを、2社間ファクタリング・3社間ファクタリングに分けて見ていきましょう。
2社間・3社間ファクタリングの仕訳例
ファクタリングの仕訳は、「誰と誰の間で取引が行われるか」によって変わります。
大きく分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つのパターンがあります。
🟢 2社間ファクタリングの仕訳
ファクタリングでは、取引の形によって仕訳の考え方が変わります。
大きく分けて「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」がありますが、
この2つの違いは、“売掛金を譲渡したか、それとも担保にしたか” という会計上の考え方にあります。
🟢 2社間ファクタリング(担保型)
2社間ファクタリングは、あなた(利用者)とファクタリング会社の2社だけで完結します。
売掛先には通知されず、資金だけを先に受け取る形です。
法的には「売掛金の譲渡」ではなく「売掛金を担保に資金を受け取った」とみなされます。
💬 仕訳例
売掛金100万円を、手数料5万円を差し引いて95万円で現金化した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 950,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 支払手数料 | 50,000 |
👉 売掛金を消して、差額を「支払手数料」として費用処理します。
※ファクタリング専用の補助科目を設ける場合は「支払手数料/ファクタリング」として管理してもOKです。
🟣 3社間ファクタリング(譲渡型)
3社間ファクタリングは、売掛先(取引先)にも通知し、承諾を得た上で行う取引です。
この場合、売掛金の権利は完全にファクタリング会社へ移転します。
つまり、会計上は「債権の譲渡=売却」になります。
💬 仕訳例
売掛金100万円を、手数料3万円を差し引いて97万円で譲渡した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 970,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 支払手数料 | 30,000 |
👉 この場合も「支払手数料」でOKです。
譲渡損として処理することもできますが、実務上は支払手数料に含めて問題ありません。
💡 まとめ
| 項目 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
|---|---|---|
| 売掛先への通知 | なし | あり(承諾あり) |
| 法的な性質 | 債権担保型(融資に近い) | 債権譲渡型(売却扱い) |
| 会計処理の考え方 | 売掛金を担保にした資金化 | 売掛金を譲渡して現金化 |
| 手数料の勘定科目 | 支払手数料 | 支払手数料 |
💬 筆者コメント
どちらの形式でも、実務上は「支払手数料」で処理して構いません。
ただし、ファクタリング取引が多い企業では、**補助科目で「ファクタリング手数料」**を分けておくと、
資金調達コストを分析しやすくなります。
💰 ファクタリング手数料と消費税の扱い
仕訳の次によく聞かれるのが、「この手数料って消費税の課税対象になるの?」という点です。
ファクタリングは“お金を受け取る取引”ではありますが、**融資とは異なる「債権の売買」**という扱いになるため、
手数料の消費税区分を正しく理解しておくことが大切です。
🟢 ファクタリング手数料は「課税取引」です
結論から言うと、ファクタリング手数料には消費税がかかります。
これは、手数料が「役務の提供(サービスの提供)」とみなされるためです。
国税庁の見解でも、ファクタリング会社が行う債権の買取に伴う手数料は、
非課税の金融取引(貸付・利息など)には該当しないと明確にされています。
👉 つまり、ファクタリングの手数料は 課税仕入れ(消費税がかかる費用) として処理します。
🧾 仕訳例(消費税処理あり)
売掛金100万円を95万円でファクタリングした(手数料5万円、消費税10%含む)場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 950,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 支払手数料 | 45,455 | ||
| 仮払消費税 | 4,545 |
手数料5万円のうち、
・45,455円が手数料の本体(課税仕入)
・4,545円が消費税(10%)
となります。
⚠️ 注意点
- 融資の利息とは違うため、「非課税」ではありません。
- 消費税の仕入税額控除の対象になる(=還付・控除可能)
- ファクタリング会社によっては、請求書内で「税込」表示しかない場合もあるので注意。
手数料を抑えたい方は、QuQuMo(ククモ)の解説記事も参考にしてください。
💬 筆者コメント
ファクタリング手数料は、融資の「利息」ではなく「手数料(サービス料)」扱い。
つまり、会計上も税務上も課税取引として処理するのが正解です。
決算や申告の際に「非課税」として処理してしまうと、後で修正が必要になることもあります。
⚖️ 経理処理で注意すべきポイント(実務上の落とし穴)
ファクタリングの仕訳はシンプルに見えますが、実務では小さな判断ミスで
「税務上の処理誤り」や「売掛金の二重計上」が発生しやすい取引でもあります。
① 売掛金の消し忘れ・二重計上
ファクタリングで資金化した後も、売掛金を帳簿上に残してしまうケースがよく見られます。
特に2社間ファクタリングでは、売掛先に通知しないため、「まだ請求中」と誤解しやすい点に注意。
👉 資金化が完了した時点で、必ず売掛金を消す(相手勘定は普通預金+支払手数料)処理を行いましょう。
② 手数料を「利息」扱いにしない
ファクタリングは融資ではないため、利息ではなく手数料です。
もし「支払利息」で処理してしまうと、非課税扱いとなり、
税務上は仕入税額控除の対象外になってしまいます。
👉 正しくは「支払手数料(課税仕入)」で処理。
消費税の申告時に控除できるようになります。
③ 消費税の処理漏れ
請求書に「税込5万円」としか書かれていない場合、
経理担当者がそのまま5万円を「支払手数料」にしてしまうことがあります。
しかし、実際には
- 手数料本体:45,455円
- 消費税:4,545円
と分けて処理しないと、決算書上の「課税仕入高」が過少計上になります。
👉 税込表示でも内訳を計算して分けるクセをつけましょう。
④ ファクタリングと手形割引の混同
どちらも「売掛債権を現金化する」点では似ていますが、
**手形割引は金融取引(非課税)/ファクタリングは債権売買(課税)**という明確な違いがあります。
👉 消費税処理が逆転するため、混同に要注意。
⑤ 決算時の債権残高の整合性チェック
ファクタリングを利用していると、売掛金残高と実際の未回収状況がズレることがあります。
たとえば、売掛金をファクタリングで現金化した後に、
その分の売掛金を帳簿上で消し忘れてしまうと、
「すでに資金化済みなのに、まだ未回収として残っている」状態になってしまいます。
💡 チェックのポイント
決算や月次締めのタイミングでは、次のように確認すると安心です。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ファクタリング契約一覧 | 今期(または当月)に資金化した請求書をリスト化 |
| 売掛金残高 | 該当する請求書の売掛金をきちんと消しているか確認 |
| 実際の未回収分 | ファクタリングに出していない・入金待ちの請求書のみを集計 |
このように整理することで、**帳簿上の「売掛金残高」と実際の未回収分(=まだ資金化していない分)**が一致しているかをチェックできます。
💬 筆者コメント
ファクタリングの経理処理で一番多いミスは、「仕訳自体の間違い」ではなく「消費税と残高管理の見落とし」です。
正しい処理を行うことで、後々の税務調査や監査対応もスムーズになります。
✅ まとめ:ファクタリング仕訳の基本を押さえよう
ファクタリングは、資金繰りをスムーズにする便利な手段ですが、
経理処理の考え方は融資や割引手形とはまったく異なります。
特に押さえておきたいポイントは次の3つです👇
- ファクタリング手数料は 課税取引(消費税がかかる)
- 仕訳は「支払手数料」でOK(2社間も3社間も同じ)
- 売掛金残高は資金化済み分を消すのを忘れずに
これらを理解しておけば、決算時の整合性チェックもスムーズになります。
💬 筆者コメント
ファクタリングの会計処理は、最初は少し戸惑いますが、
「融資ではなく、売掛金の売却」と考えるとシンプルです。
税務署や会計士からの質問にもスッと答えられるようになりますよ。
💡 次に読むと理解が深まる記事
ファクタリングを会計の面から理解できたら、
次はサービス選びの実例を見てみましょう。
「どの会社を選ぶべきか」を比較した記事を読むと、
実務に落とし込みやすくなります。
<div class=”wp-block-cocoon-blocks-button-1 aligncenter button-block”> <a href=”/factoring-comparison/” class=”btn btn-m btn-circle btn-shine has-background has-border-color has-teal-background-color has-black-border-color” rel=”noopener”> 🔍 ファクタリング会社を比較してみる > </a> </div>


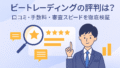
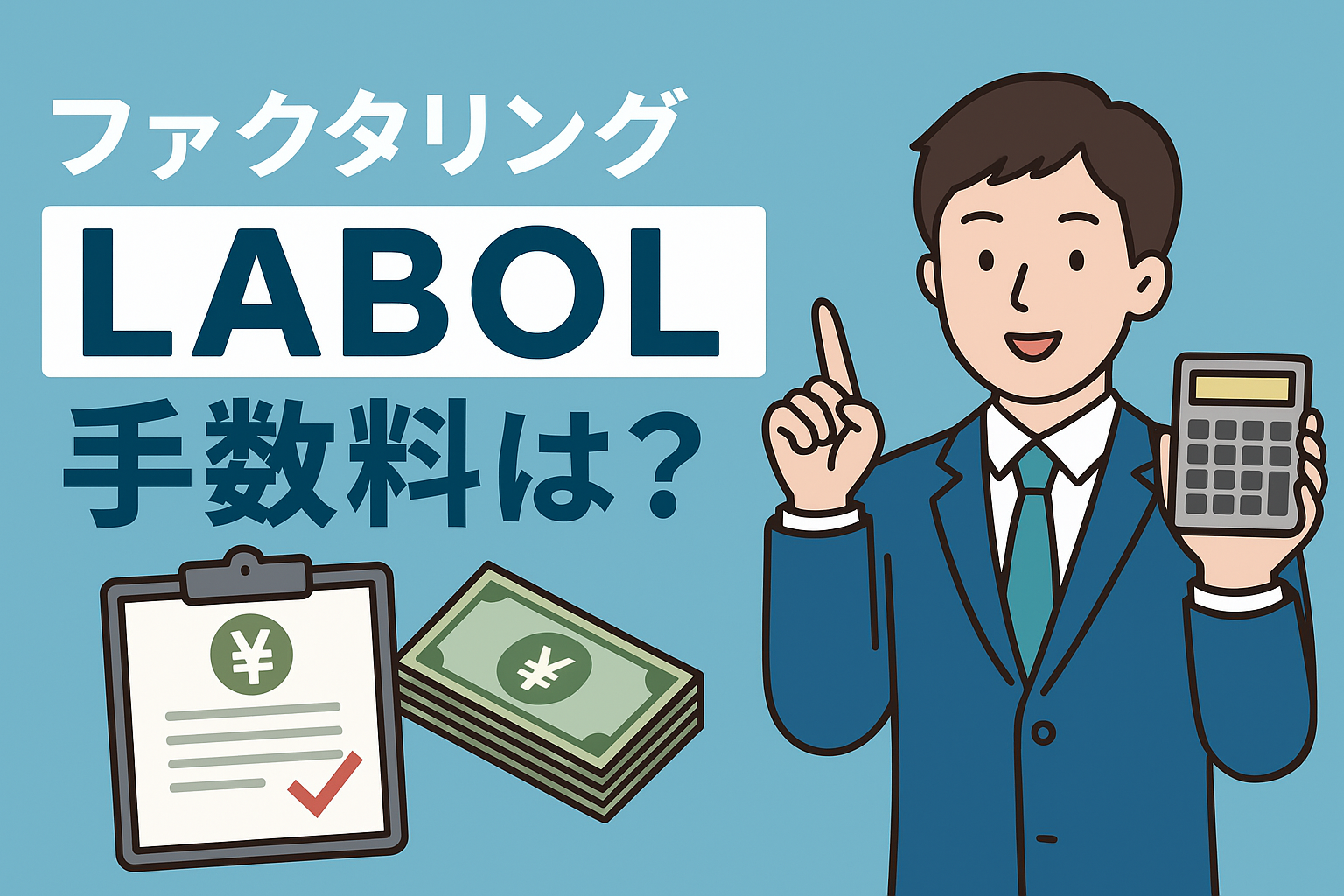
コメント